
WEB招待状を送るときのメッセージ例文とマナーを相手別に解説
WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。
カテゴリから探す

WEB招待状(無料)

招待状

席次表

プロフィールブック

席札

エスコートカード

その他のペーパーアイテム

引き出物カード

ヒキタク(引き出物宅配便)

その他の引き出物

プロフィールムービー

オープニングムービー

その他のムービー

プチギフト

両親プレゼント

ウェルカムボード


























ウェルカムスペース・
演出小物

披露宴・二次会景品

結婚式アルバム

コスメ・美容

ウェディングアクセサリー

ドレス・タキシード

フォトウェディング・前撮り

セルフフォトスタジオ

ブライダル保険

結婚内祝い・お返しギフト

カタログギフト

ソーシャルギフト

結婚式 電報・祝電

報告はがき・年賀状・
喪中はがき
グループサイト
イベント情報

結婚式で必要となるペーパーアイテムには、招待状や席札、席次表など、たくさんの種類があります。
どのペーパーアイテムも、新郎新婦とゲストを繋ぐための大切なものだからこそ、素敵なものを用意したいですね。
この記事では、結婚式に必要なペーパーアイテムとはどんなものなのか、どんなことに注意して準備をすればいいのかをお伝えします。
また、結婚式準備に便利なペーパーアイテムセットについてもご紹介します。
ペーパーアイテムとは、結婚式で必要となる紙製のアイテムのことを言います。
結婚式で使われるペーパーアイテムには、招待状や席次表、席札やプロフィール表など、たくさんの種類があります。
どのペーパーアイテムも新郎新婦とゲストを繋ぐための大切な役割を持っていますので、心を込めて素敵なものを準備しましょう。
結婚式で使用するペーパーアイテムの中で、ゲストが最初に触れるのが招待状です。
いつ・どこで・誰と結婚式を執り行うのかを記載したペーパーアイテムで、結婚式の2~3ヶ月前にはゲストへ発送するのがマナーとなっています。
この招待状の作成が遅れると、結婚式に招待するゲストを確定するのが遅くなってしまい、後に作成する席次表や席札も遅れてしまいます。
招待状は結婚式の3ヶ月前ごろから準備をし、余裕を持って発送するようにしましょう。
結婚式の招待状に書くべき内容は、次の通りです。
・本文…頭語(拝啓・謹啓など)、時候の挨拶(春暖の候・初秋の候など)、招待の言葉を書き、結語(敬具・謹白など)の順番で書きましょう。
・差出日…「〇月〇日吉日」と書きましょう(縁起のいい日に送ったということを示すため)。
・差出人…結婚式の主催者の名前を書きましょう。
・挙式、披露宴の日時…挙式や披露宴の日付、開始時間、受付の時間などを書きます。
・結婚式を挙げる場所…結婚式場の名前、住所、電話番号を書きます。
・返信ハガキの締切日…結婚式の約1ヶ月前(発送してから約1ヶ月後)を目安にしましょう。大安か友引の日に設定するとベターです。
招待状には本文や挙式日を記載した本状とは別に、いくつか同封すべきものがあります。
・返信ハガキ…結婚式に招待するゲストの出欠を確認するためのものです。返信ハガキには忘れずに返信用の切手を貼っておきましょう。
・結婚式場までの地図…ゲストがスムーズに結婚式場に来られるよう、地図を同封しておきましょう。地図は結婚式場が用意してあるものを使用するか、なければ自分たちで作成することとなります。
・付箋…付箋とは結婚式の受付や祝辞・余興などをお願いする相手に同封するペーパーアイテムです。招待状に付箋を同封することで正式な依頼となります。
結婚式の招待状を準備するにあたり、注意しておきたいポイントが3つあります。
結婚式の招待状にはゲストの名前や住所を記載する必要があります。
名前の漢字や住所が間違っているとゲストに対して失礼となってしまいますので、招待状を送りたい旨を伝えると同時に、名前の漢字や住所もしっかりと確認しておきましょう。
親しい間柄でも念のために確認しておいたほうが安心です。
結婚式の受付や余興・乾杯の挨拶などをお願いする相手には、招待状と一緒に付箋を送ることになります。
しかし、突然招待状に付箋が入っていると、ゲストは驚いてしまいます。
まずは、招待状を送る前に直接祝辞や受付をお願いしたい旨を伝えておき、了承を得られてから招待状に付箋を同封して発送するのがマナーです。
結婚式の招待状には、通常の切手ではなく慶事用の切手を貼りましょう。
郵送料金不足の状態で発送してしまうとゲストが不足分を支払うことになります。
そのようなことにならないよう、同封物をすべて入れた状態で招待状の重さを量ってから切手を購入しましょう。
郵便局の窓口で量ってもらうと確実です。
席次表とは、結婚式当日に受付を済ませたゲストが受け取るペーパーアイテムです。
席次表には披露宴会場のテーブルレイアウトが記載されており、席次表を見ることでどこに座ればいいのかをゲストが一目で把握することができます。
また、席次表はほかにどんなゲストが参加しているのかを知ってもらうこともできます。
最近では、席次表に新郎新婦のプロフィールや料理のメニューが書かれていることも多いです。
席次表には、結婚式に招待したゲストの名前と肩書きを記載します。
もしゲストの名前の漢字や肩書きが間違っていた場合、失礼に当たるだけではなく結婚式自体がゲストにとって残念な思い出に変わってしまう可能性もあります。
席次表に書く名前の漢字や肩書きは事前にしっかりと確認して、間違いのないように記載しましょう。
結婚式はおめでたい場であるからこそ、ゲストにとっても過ごしやすい席順を考えましょう。
上座や下座など最低限のマナーは守るべきですが、同じテーブルには仲のいいメンバーを集めるなど、ゲストにとって過ごしやすい席順にすることが大切です。
席札とはネームプレートのようなもので、ゲストが座る席に前もって置いておくペーパーアイテムです。
ゲストは席次表で自分が座るテーブルを確認しつつ、席札を見て自身の席を改めて確認します。
ゲストがどこに座ればいいのかをわかりやすくするペーパーアイテムなので、必ず準備しておきましょう。
招待状や席次表と同じく、席札に書くゲストの名前も漢字の間違いがないかなど、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。
完成後にプランナーさんなどの第三者に確認してもらっておくと安心です。
席札はテーブルの上に置いておくペーパーアイテムなので、ゲスト同士で隣の席などの席札が目に入ってしまうことがあります。
席札のメッセージの文量に差があると、ゲストが嫌な気持ちになってしまうこともあるので、ゲスト全員の文量が同じぐらいになるようにしましょう。
プロフィールブックとは、新郎新婦の写真、趣味、出身地などを記載したペーパーアイテムのことで、ゲストに新郎新婦のことをより知ってもらうことができます。
基本的なプロフィールはもちろん、新郎新婦が出会ったきっかけや思い出のデート、相手の好きなところなどを書くカップルも多いです。
披露宴が始まるまでの間にプロフィールブックを見るゲストも多く、ゲスト同士の会話のきっかけにもなります。
最近では席次表にプロフィールを記載する新郎新婦も増えてきています。
メニュー表は結婚式当日に出す料理やドリンクのメニューを記載したペーパーアイテムです。
料理のメニューはもちろん、ゲストが注文できるドリンクのメニューも確認することができるので準備しておくと親切です。
料理メニューやドリンクメニューに間違いがないか、事前にプランナーさんを通してシェフに確認しておくようにしましょう。
席次表やプロフィールと一緒にメニュー表も記載する新郎新婦が増えてきています。
結婚式で必要となるペーパーアイテムは、招待状や席次表・席札などたくさんの種類があるので、全てを自分で準備するのはとても大変なものです。
しかも、ペーパーアイテム以外にも、衣装やフラワー類・メニュー決めなど、準備しなければいけないことはたくさんあります。
そこでおすすめなのが、印刷込のセットを購入するということです。
印刷込のセットとは、デザインや文字がすでに印刷されているアイテムのことを言います。最近では、ネットでさまざまなデザインのセットが販売されているので、自分好みのデザインや、結婚式のテーマに合ったデザインを見つけることもできるのではないでしょうか。印刷込のセットを購入すれば、自分で行う作業は本文や名前に間違いがないかの確認や、招待状に同封するものをセットするだけです。
印刷込のセットを購入して時間や手間を省いた分、他の結婚式準備に時間を充てることもできます。新郎新婦が2人とも仕事をしている場合や、結婚式までの日数があまりないという場合は、ぜひ印刷込のセットを活用しましょう。
自宅にプリンターがなかったり、パソコン操作が苦手だという人にも、印刷込のセットがぴったりです。
結婚式で必要となるペーパーアイテムは、招待状や席札、席次表などたくさんの種類があります。
いずれも結婚式に来てくれるゲストと新郎新婦を繋ぐ、とても大切なアイテムです。ペーパーアイテムセットなども活用しながら、素敵なペーパーアイテムを準備しましょう。

WEB招待状のメッセージ例文を相手別にご紹介。友達や親族、上司向けの丁寧な文例やカジュアルな文例から、ゲストとして返信する際の文例まで詳しく解説。

「招待状の入れる向き」「手渡しする際のマナー」「招待状やハガキの入れ方」etc…実は知らない?封筒のマナーとは
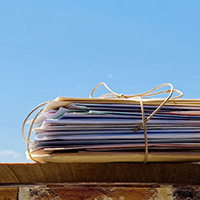
結婚式の招待状に関する疑問と郵送する時に気を付けてほしいことを紹介します

返信ハガキの書き方の注意点をはじめ、よくある質問について解説!

招待状の準備で忘れがちな「付箋」。よく使う付箋の文例や選び方をおさえてしっかり準備しておきましょう

結婚式の招待状を出席で返信したのに欠席しなければならなくなったときのマナー、連絡方法、ご祝儀の有無をまとめて紹介